最近、「SASUKE TOKYO」が開発した『再会XR』というサービスのニュースを目にしました。
これは、愛するペットの3Dデータを取得し、スマホやARゴーグルを通じて、まるで生きているかのようにペットと“再会”できるという、まさに未来のような体験を提供するサービスです。2024年1月12日(金)に正式リリースされ、今、注目を集めています。
さらに驚いたのは、生成AIの技術を活用し、ペットのしぐさや行動、鳴き声までもリアルに再現できるという点です。
テクノロジーの進化によって、「もう一度会いたい」という多くの飼い主の願いが、少しずつ現実のものになろうとしています。
私自身、以前に愛犬を亡くし、大きな悲しみと喪失感を経験しました。
だからこそ、「再会XR」のようなサービスが、ペットロスに苦しむ方々の心の支えや癒しの一歩になる可能性を感じています。
もちろん、こうした新しい技術と同時に、亡くなったペットを丁寧に見送り、想いを込めて供養することも、心の整理には欠かせない大切な時間です。
愛するペットとの最期の時間を、心を込めて
大切な家族とのお別れに、後悔のない時間を過ごすために、ペット専門の葬儀サービスでは、納得のいくお見送りができるよう、丁寧なサポートが行われています。
火葬や供養の方法について迷われている方も、まずは一度相談してみてください。
心を込めて見送ることは、ペットへの感謝と愛情を伝える大切なプロセスです。
私が犬を飼いたいと思った原点
図鑑で見たミニチュアシュナウザーの記憶
初めて犬を飼うことになったのは、長女が中学1年生、次女が8歳のときでした。
ある日、友人に誘われて立ち寄ったペットショップで、ミニチュアシュナウザーのメスが2頭、同じケージの中で仲良く遊んでいる姿を目にしました。その瞬間、若い頃に本屋で立ち読みした『世界の犬の図鑑』を思い出しました。
その図鑑では、見開きページでさまざまな犬種が紹介されており、子犬と成犬の写真が並べて掲載されていました。小さな頃と大きくなった後で、見た目の印象が大きく変わる犬種が多かったことが記憶に残っています。
なかでも特に目を引いたのが、ミニチュアシュナウザーです。子犬のときの愛らしさはもちろん、成犬になったときの凛々しさと、子どもの頃の可愛らしさをそのまま目元に残している姿がとても印象的でした。その頃から私は、いつか犬を飼う機会があれば、ミニチュアシュナウザーを迎えたいと、密かに夢を抱くようになったのです。
犬を飼うと決めた日、家族の心に芽生えた優しさ
子どもたちが学校から帰ってくるのを待ち、一緒にペットショップへ向かいました。目的は、2頭いる子犬のうち、どちらか1頭を選ぶこと。店員さんによると、この2頭は姉妹で、体の小さいほうが姉、少し大きいほうが妹だそうです。
今振り返れば、2頭とも一緒に迎えてあげるべきだったと感じます。けれど、当時は初めて犬を飼うという緊張や不安もあり、そこまでの余裕はありませんでした。私たちはしばらくの間、2頭の様子をじっくりと観察しました。その後、長女が選んだのは、妹のほうでした。
選んだ理由は、その子犬が少し引っ込み思案で、警戒心が強かったから。ケージから出してもすぐには走り回らず、じっと周囲の様子をうかがっていた姿が、長女の心に響いたようです。子どもながらに、その子犬が他の子よりも特別な心配や愛情を必要としていると感じ取ったのでしょう。
それは、私が今まで見たことのない長女の一面でした。おそらく、犬を飼うことがなければ気づかなかった一面だったかもしれません。こうして我が家に、初代ミニチュアシュナウザーの「メル」がやってきたのです。

愛犬メル
ミニチュアシュナウザー、ソルト&ペッパー
まつ毛が長く、お目眼パッチリ♫
体型は小さめで、5キロ前後をいつもキープしていました。
ペットとの絆がもたらす癒しと成長
ペットは、家族の一員として長い時間を共に過ごし、特別な絆を築いていきます。その忠実で穏やかな存在は、私たちの孤独を和らげ、喜びを倍増させてくれます。日常の中で癒しを与えてくれる、かけがえのない存在です。
我が家の愛犬・メルも、まさにそうした存在でした。娘たちがケンカをすればそっと間に入って仲裁し、私が娘を叱っていると、決まってその子のそばに寄り添い、まるで慰めるように静かに寄り添っていました。言葉こそ話さなくても、メルはいつも家族の空気を敏感に感じ取り、すべてを理解していたように思います。
そんなメルは、鼻腔内腫瘍という病と闘い、14歳と2ヶ月の生涯を終えて、静かにお空へと旅立っていきました。
初めて経験した悲しみ
喪失感と悲しみ
愛犬を失ったとき、胸を締めつけるような悲しみと後悔が、心に押し寄せてきます。
「もっとこうしてあげていれば……」「あの時の判断は間違っていたのではないか……」
そんな思いが頭の中を何度もめぐり、後悔や悲しみは、時が経つほどに増していくこともあります。
ペットは、無償の愛情を私たちに注いでくれる存在です。
いつの間にか日常の中に溶け込み、いなくなって初めて、その存在の大きさに気づかされるのです。
対処が難しい感情
ペットロスは、他の喪失体験と同じように、心の整理が難しい感情を伴います。
深い悲しみ、喪失感、そしてぽっかりと空いたような孤独感・・・
それらが一度に押し寄せ、心の中が混乱してしまうこともあります。
「大切な存在を失う」という事実を受け止めることは、とてもつらく、簡単なことではありません。
日常に当たり前のようにいた存在がいないという現実に、心がついていかないのです。

数年経った今でもふと涙が出てきます。その感情は、「寂しい」というだけではなく、愛らしかった姿を思い出し、懐かしむ時でさえも涙が出てくるのです。人間の感情はなんと複雑なものなのでしょうか。
ペットロスの克服方法
悲しみを受け入れる
ペットロスを乗り越えるための第一歩は、悲しみを素直に受け入れることだとよく言われます。
感情を押し殺すのではなく、自分の悲しみをきちんと受け止め、言葉にしたり、表現することが大切なのだそうです。
私自身、もともと開けっぴろげな性格だと思っていますし、周囲にいろいろと話すこともありました。
それでも振り返ってみると、気持ちが少しずつ整理されるまでに、2年から3年ほどの時間がかかったように思います。
サポートを求める
ペットロスの悲しみに一人で立ち向かうのは、想像以上に心に負担がかかります。
そんなときは、信頼できる友人や家族、あるいは専門家のサポートを受けることが、心の支えになることがあります。
専門家であれば、感情の整理や受容を助ける適切なアドバイスや支援を提供してくれるでしょう。
「一人で抱え込まないこと」は、ペットロスと向き合ううえでとても大切な姿勢です。
新たな趣味や活動を見つける
悲しみを抱えながらも、少しずつ前を向くきっかけとして、新しい趣味や活動を始めることも有効です。
趣味や好きなことに取り組む時間は、気分転換になり、心に小さな喜びをもたらしてくれます。
そのプロセスが、やがて悲しみに立ち向かう力へと変わっていくかもしれません。
また、活動を通じて新しい出会いがあることも。新たな人間関係が、少しずつ心を和らげてくれることもあるでしょう。
記憶を大切にする
愛したペットとの思い出を、無理に忘れようとする必要はありません。
写真や動画など、かけがえのない記憶を大切に残していくことも、ペットロスを乗り越える一つの方法です。
私がよく愛犬を連れて出かけていた公園には、今も多くの愛犬家が散歩に訪れています。
顔見知りになる方も多く、自然と会話が生まれる場所でもあります。
その中に、数年前に愛犬2頭を亡くしたという、70代の男性がいらっしゃいます。
「年齢的にもう新しく犬を飼うことはないけれど、こうして写真を持って公園を歩くのが楽しみなんです」と、穏やかな笑顔でおっしゃっていました。
亡き愛犬たちとの思い出を胸に、大切に過ごすその姿に、私は深い共感を覚えました。
ペットロスの克服方法に、記憶を大切にするというのがあります。SASUKE TOKYOという会社が提供するサービスは、愛するペットの3Dデータを取得し、スマホやARゴーグルを使って蘇らせる(再会)ことができるというものです。さらに、生成AIを使って、今までの行動や鳴き声も再現できるとのこと。デジタル技術の進歩は凄いですね!いつでも愛するペットに会えると思えば、喪失感から少しでも解放されるのではないでしょうか。
まとめ|愛する存在を失った悲しみと、前を向くためにできること
ペットは、ただの動物ではなく、私たち家族の一員として日々を共に過ごし、深い絆を育んでくれる存在です。
だからこそ、その別れは計り知れない悲しみや喪失感をもたらし、ときに心を深く揺さぶります。
私自身も、大切な愛犬・メルとの別れを経験し、その痛みと向き合ってきました。
悲しみを受け入れること、支えてくれる人に頼ること、思い出を大切にすること。
少しずつ時間をかけながら、自分なりの癒し方を見つけていくしかないのかもしれません。
そして同時に、最期の時間を心を込めて見送ることも、ペットへの深い愛情の証です。
納得のいくお別れができるよう、ペット専門の葬儀サービスなど、必要なサポートを受けることも大切な選択肢のひとつです。愛する存在と過ごした日々を胸に、少しずつでも、前を向いていけますように。


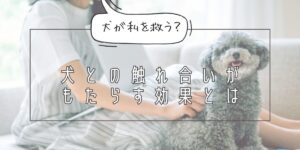


コメント